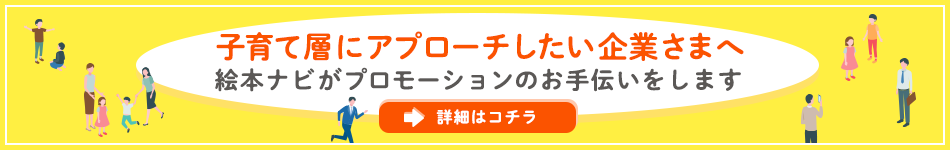旅と人を描いてきた絵本作家・小林豊さんが見つめた故郷・東京の姿が絵本に『えほん 東京』

東京──と聞くと、みなさんはどんなまちをイメージするでしょうか?
高層オフィスビルが立ち並ぶ「ビジネスのまち」?
きらびやかなウインドウが並ぶ「ショッピングのまち」?
それとも?
2020年のオリンピックを目前にして世界から注目を集めている東京のまちですが、イメージするものは人それぞれに違うかもしれません。
『えほん東京』(小林豊/作・絵) は、「東京の素顔」をこれまで誰も見たことのない手法で教えてくれる絵本です。
数多くのノンフィクション作品を手がけてきた絵本作家・小林豊さんの魅力
作者の小林豊さんは、『せかいいちうつくしいぼくの村』(ポプラ社)をはじめとした「ぼくの村」三部作で、戦乱の続くアフガニスタンに生きる少年ヤモの目を通して、そこに暮らす人びとの心のやさしさ、力強さと、「生きること」のすばらしさを描きました。
また、『えほん北緯36度線』や『とうさんとぼくと風のたび』(ともにポプラ社)では、登場人物の「旅」を通して、さまざまな土地で生きる人間とその文化を、豊かな色彩と情感に満ちた筆致で描き出しています。
『えほん東京』は、旅を描き、人間を描きつづける絵本作家・小林豊さんが、ご自身の出身地である「東京」を独自の手法で描いた絵本です。
時間を超えてまじりあった「東京」と「江戸」の姿
物語は、さくらの花びらが舞う季節に、主人公のぼくが「どこか行こうよ」と、おじいちゃんを誘うところからはじまります。
「ねえ。どこか遠くへ行こうよー。ぼく、海にいきたい」
「海なら、おまえの目のまえにあるぞ」
「?」
まわりは見慣れた住宅街で、近くに海なんかあるはずがありません。
ところが、おじいちゃんが指さした先にあるお稲荷さんの鳥居をくぐると、きらきら輝く青い水平線が向こうに広がっています。
どこからか聞こえてくるのは、魚を売る声や宿屋にお客さんを呼びこむ声。
「ここは品川の宿。東海道の宿場町だ」と、おじいちゃん。

そう。
本書は、時間をこえてまじりあった「現代の東京」と「江戸」の“まち”が、見開きいっぱいに描かれた絵本なのです。
旧石器時代の遺跡や古墳なども多く発掘されています。
そして、1590年、はじめて江戸に入った徳川家康により、計画的にまちづくりがされた都市です。
これにより、自然の地形をいかしながら江戸城を中心に〈の〉の字型の「水の道」がつくられました。
江戸城のまわりをとりまく運河は、麹町台周辺の湧水を利用して内濠とし、谷筋から流れでる河川とつながります。流れは一度大川(いまの隅田川)に出てから、ふたたび〈の〉の字を描くように千代田区あたりを一周します。これが外濠です。
終点がなく拡大する〈の〉の字型の「水の道」、そして、武蔵野台地から流れこむ「風の道」が、江戸のまちの原型で、これはいまの東京の姿につながっているのです。

「江戸時代にはまちの主役だった運河だけれど、いまは埋められ忘れ去られている。丘も谷も海辺にも高層ビルが建ちならび、見通しも風通しもわるくなった。いまの東京は親(江戸)の遺産を食いつぶす『道楽息子』の姿かもしれない」と、小林豊さんは解説ページに書いていらっしゃいます。
そして、「どんなにコンクリートやタイルできれいに着飾っても、東京の自然は生きていて、まちのそこここに脈々と息づく人びとのくらし=風景が見えてくる」と。
絵本作りのとちゅう、小林さんと編集担当者さんとで、上野から浅草までの東京散歩に出かけたことがあったそうです。
浅草神社の裏手あたりで、「ほら、ここの地面を見てごらん」と小林さんに言われて、ふっと目線をさげると、東に向かってごくごくわずかに土地がさがっていることがわかります。
写真に撮ってもわからないような、わずかな傾斜です。
「この傾斜を〈感じる〉と、海が近いってことがわかるでしょう」と、小林さん。
 隅田川沿いを吾妻橋へ向かって歩く。後ろ姿は小林豊さん
隅田川沿いを吾妻橋へ向かって歩く。後ろ姿は小林豊さん
わたしたちの足もとには、自然があり、そしてその土地で生きてきた人びとがいる。
もちろん東京以外の地域にお住まいの方にもおすすめします。この物語は東京が舞台になっていますが、みなさんがお住まいのまちの素顔も、きっとみなさんの目のまえに立ちのぼってくるはずです。

|
この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |




 絵本・本・よみきかせ
絵本・本・よみきかせ 






 あそび
あそび