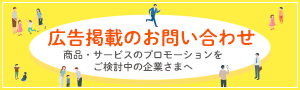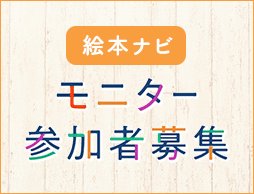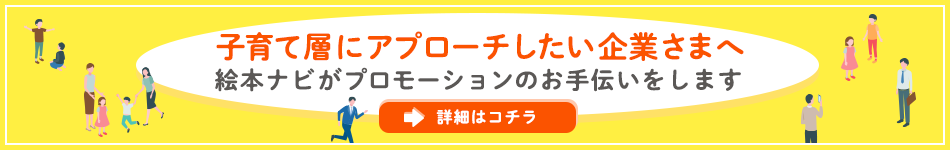幼児教育には絵本がよい?効果や年齢別のおすすめ10選、読み聞かせのコツを紹介
 (1).jpeg)
幼児教育にはさまざまな種類や方法がありますが、中でも手軽に始められるものとして、絵本の読み聞かせがおすすめです。
しかし、絵本を活用するうえで、どんな絵本を選んだらよいか、またどんな風に読み聞かせを行うのがよいか悩む方もいるでしょう。
本記事では、幼児教育の観点から見た絵本の読み聞かせをするメリットや、年齢別のおすすめの絵本と選び方、読み聞かせのコツなどを紹介します。
幼児教育とは?
幼児教育とは、その名の通り小学校就学前の幼児に対して行う教育のことで、幼稚園や保育所などの施設、地域社会、家庭など、幼児が生活する全ての場において行われる教育を指しています。
幼稚園や保育所などの施設では、集団行動の中で教員に支えられながら家庭ではできない体験をし、地域社会ではさまざまな人との交流や自然との触れ合いを通して豊かな体験を得ることができます。
家庭では、愛情やしつけなどを通して成長の基礎となる心身の基盤を形成していきます。
幼児教育の目的は、内面に働きかけて個人の持つよさや可能性を見出し、その芽を伸ばすことです。目先の結果のために行うものではなく、確かな学力や豊かな人間性、健康・体力を含む「生きる力」の基礎を育成する役割を担っています。
幼児教育で絵本の読み聞かせをするメリットや効果
幼児教育には、モンテッソーリ教育やシュタイナー教育、ピラミッドメソッド幼児教育、七田式教育などさまざまな種類や方法があります。
その中でも、特別なおもちゃや教材などを必要とせず、より手軽に始められるのが絵本の読み聞かせです。
ここでは、幼児教育で絵本の読み聞かせをするメリットや効果について紹介します。
親子の関わりが増える
絵本の世界を親と子どもで一緒に楽しむことで、同じ時間を過ごしながら同じ体験を共有します。
添い寝をしながら、あるいはお子さんをひざの上に座らせて行う読み聞かせの時間は、親子の信頼を深める大切なコミュニケーションとなるほか、子どもにとって親の愛情を感じられる幸せなひとときとなります。
豊かな感性を養える
絵本の読み聞かせを通して、子どもは登場人物の行動や心情を自分のことのように疑似体験したり、自分の経験を結び付けて想像したりすることを楽しみます。
登場人物になりきって想像の世界を自由に楽しむことで、うれしさや悲しさ、痛みなどさまざまな感情に触れ、他人の感情や思いを知ることができます。
幼児期からの読み聞かせで多くの物語に触れることは、豊かな感性や想像力などを身につけて社会の中で生きる力の基礎を育みます。
集中力を高められる
信頼できる大人と同じ物語を楽しむ時間を共有すると、子どもは安心して絵本の世界に入り込みます。
「このあとどんなことが起こるのだろう?」「次はどんな絵かな?」と物語に引き込まれる経験を繰り返すことで、徐々に集中力が高まっていきます。
読解力や言語能力を高められる
絵本には、美しい言葉がたくさんつづられています。子どもは耳で言葉を覚えどんどん吸収していくため、日常会話以外のさまざまな言葉に触れる機会が増えることで語彙力が高まります。
語彙力や言語能力を身につけることは、読解力やコミュニケーション能力の向上にもつながるでしょう。
手軽に始められる
絵本は、特別な準備や知識が必要なく、より手軽に始めることができる幼児教育のひとつです。
種類が豊富で内容も豊かでありながら、何度も繰り返し楽しめる点も魅力で、育児や保育・教育においても欠かせないものです。
【年齢別】幼児教育におすすめの絵本と選び方
幼児教育におすすめの絵本と選び方を、年齢別に紹介します。
0〜1歳児の場合
個人差はあるものの、生後10ヵ月頃から言葉を聞きながら絵本を楽しむことができるようになります。
この時期には、子どもの生活の中で登場する食べ物や動物、乗り物など身の回りのものを描いた絵本や、音の響きやリズム、色や形を見ながら親子で楽しめる絵本がおすすめです。
また生後3~5ヵ月頃から少しずつものや色を認識できるようになります。色がはっきりとしたものやカラフルな絵本を選ぶようにしましょう。
はじめてのかたち FIRST LOOK
したく
6か月からのあかちゃんのための絵本シリーズ(全5冊)。身近なもの、人をとりあげて、あかちゃんの興味をそそります。お母さんといっしょに楽しめる、文字のない知育絵本です。あかちゃんが触ったり、ひっくり返したりして遊ぶことを充分考えて、角の丸い丈夫な装丁にしました。
2歳児の場合
2語文や3語文を話せるようになるなど言葉の面で大きな成長が見られるこの時期には、言葉の響きやリズム、韻などのおもしろさが味わえる絵本がおすすめです。
絵本で覚えた擬音やリズムを自ら繰り返すなど、物語とはまた違った絵本の楽しみ方を体験することができます。
まだ難しい表現は理解できないので、目や耳で覚えやすい「ワンワン」「ビュウビュウ」のようなオノマトペがたくさんでてくるシンプルな絵本を選ぶのもポイントです。
なお、オノマトペは自然界で発生する音や状態の変化などを模して表現する擬音語や擬声言語、擬態語などの総称です。
3歳児の場合
3歳頃になると、何でも自分でやりたいという自我が芽生え始めます。この時期には、歯磨きや排せつ、着替えなどの生活習慣をテーマにした絵本を選んでみると、実際の生活にも役立ちます。
また、3歳児でも理解できるようなシンプルなストーリーの絵本も取り入れていきましょう。
とくに擬音が多く使われている絵本や音の響きがよい絵本などは、子どもの心を掴みやすくまた読みたいという意欲にもつながるためおすすめです。
三びきのやぎのがらがらどん
山の草をたべて太ろうとする3匹のヤギと、谷川でまちうけるトロル(おに)との対決の物語。物語の構成、リズム、さらに北欧の自然を見事に再現したブラウンの絵、完璧な昔話絵本です。
4歳児の場合
行動範囲が広がりさまざまなことに興味を示す4歳児は、頭の中が常に「なぜ?」の疑問でいっぱいです。
4歳児は好き嫌いもはっきりしてくるため、子ども自身が興味を持つテーマや好きなものについて描かれている絵本を選ぶのがおすすめです。
また、感情移入できるようなストーリー性のある絵本も楽しめるようになってくるため、さまざまなシチュエーションの絵本を取り入れましょう。
絵本選びに困った場合は、以下の絵本もおすすめです。
かいじゅうたちのいるところ
かいじゅうの国をたずねよう。コルデコット賞を受賞し、
世界中の子どもたちをひきつけてやまないセンダックの代表作。
子どもの内面のドラマをみごとに描いて、今世紀最高の絵本と言われています。
5〜6歳児の場合
長い物語も楽しめるようになるこの時期は、内容がしっかりしていて好奇心がそそられるような絵本を選びましょう。
登場人物の心情を自分のことのように感じ取る力も備わってくる時期なので、メッセージ性のある絵本でさまざまな事柄について深く考えるのもよいです。
表情や表現から相手の気持ちを読み取れるようになってくるので、思いやりや仲直りがテーマの本などもおすすめです。
また、非日常の物語やファンタジー系の絵本を選ぶと、より好奇心や想像力を働かせながら独自の世界を楽しむことができます。
あまがえるの たんじょう
『あまがえるのかくれんぼ』『あまがえるのぼうけん』に続く
人気シリーズ最終章。“命の輝き”を美しく描く。
●『あまがえるのかくれんぼ』『あまがえるのぼうけん』に続く、シリーズ第三弾・最終章。
●繁殖からおたまじゃくし、あまがえるになるまでの3匹の成長と出会いの物語を、透明感溢れる水彩でみずみずしく描いた科学ファンタジー。
●小さな生き物の命の尊さや生き様を通して、子どもたちに、未来への希望と生きる力をお届けします。
夜の水辺では、かえるたちが大合唱。
「きゃっ きゃっ きゃっ きゃっ」と鳴くのは、あまがえるです。
しばらくすると、たまごから小さなおたまじゃくしがかえり……。
小学館児童出版文化賞受賞作家 舘野鴻と、生物画家 かわしまはるこが描く、
「3びきのあまがえる」シリーズ第三弾。3匹の誕生から出会いの物語。
あまがえるも私たち人間も同じ―命の輝きに満ちた美しい作品です。
幼児教育で絵本の読み聞かせをする際のコツ
 (2).jpeg)
幼児教育として絵本の読み聞かせをする際には、以下のようなコツを念頭に置きながら行いましょう。
ゆっくり・はっきり読む
読み聞かせは朗読する人の声を聞くため、子どもが安心して聞くことができるようなトーンを心がけましょう。
また子どもが聞き取りやすいようにゆっくり・はっきり読むことも大切です。
過度な演じ分けはしないようにする
物語の流れや登場人物の特徴の違いを出そうと、強弱を付けたり声の質、トーンを変えて過度に表現することは控えましょう。
読み手が過度に演じ分けを行うと、子どもの物語や登場人物に対する印象の偏りや心情理解を妨げてしまう可能性があります。
子どもが物語に没頭できるように、適度な表現に留めて子ども自身の想像力や創造力を引き出してあげることが大切です。
年齢に合わせた絵本を選ぶ
子どもの年齢や成長によって、読み聞かせに適している絵本は異なります。
絵の雰囲気や色使い、文字数、構成、テーマなど、その絵本が子どもの成長過程に合っているかを考えながら選ぶようにしましょう。
絵本に記載されている対象年齢を参考にするのもポイントです。
絵本の絵がよく見えるようにする
絵本の読み聞かせは、耳で聞くと同時に目で見ながら楽しむものです。子どもから絵本の絵がよく見えるように、読み聞かせを行う環境や絵本の持ち方に配慮しましょう。
また内容によっては絵本を揺らしたり振ったりして楽しむものもありますが、過度に動かすと見づらくなり子どもの集中力を妨げる恐れもあるため、適度に行うことが大切です。
子どもの幼児教育には絵本を活用しよう
数ある幼児教育の中でも、赤ちゃんの頃からより手軽に行える手段として絵本がおすすめです。
絵本の読み聞かせは、語彙力や集中力の向上などさまざまな教育的効果が期待できるほか、親子のコミュニケーションの機会としてもよいものです。
幼児教育に絵本を取り入れる際は、年齢や成長に合わせた絵本を選び、子どもが物語に没頭できるような読み方、環境を意識しましょう。選び方やおすすめも参考にしつつ、お子さんの幼児教育に絵本を活用していきましょう。

|
この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |




 まなび
まなび 
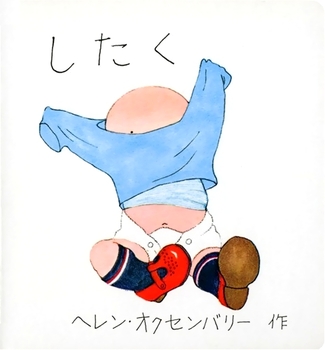










 絵本・本・よみきかせ
絵本・本・よみきかせ 

 ライフスタイル
ライフスタイル