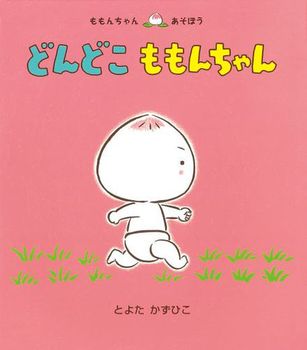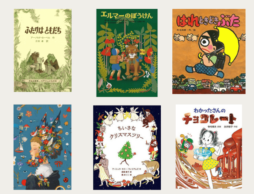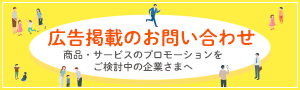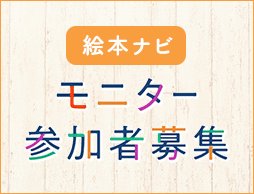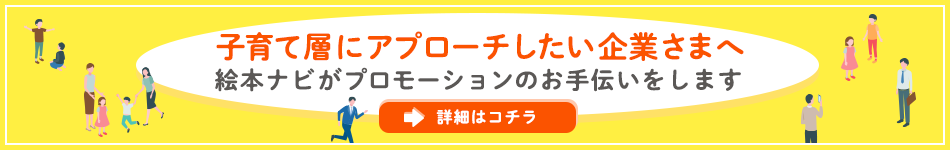読み聞かせはいつから始める?効果やおすすめの絵本も解説
 (1).jpeg)
「絵本の読み聞かせはいつから始めるべき?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
絵本の読み聞かせは、子どもの成長や発達にとってさまざまな効果が期待できます。
さらに親子の信頼関係を深めるスキンシップとしても大きな役割を持つため、言葉が分からない赤ちゃんにもぜひ積極的に取り入れていきたいことのひとつです。
本記事では、絵本の読み聞かせはいつから始めるべきか、また読み聞かせにおすすめの絵本を年齢別に紹介します。
絵本の読み聞かせとは?
絵本の読み聞かせとは、読み手が本や物語を声に出して朗読し、聞き手はそれを聞くことで楽しみや学びを得るものです。「読み語り」「読み合い」とも言われ、本と子どもを結ぶ重要な手段とされています。
絵本の読み聞かせを行うことで、言語の発達や読解力の向上、さらに想像力や共感力、集中力など、学習の基盤を築きさまざまな成長や発達を促すことができます。
親子のコミュニケーションツールとしてはもちろん、全国の図書館や学校、子育て支援センターや保育現場などでも盛んに取り入れられています。
絵本の読み聞かせはいつから始めるべき?
絵本の読み聞かせを始める時期には、「何ヵ月から、何歳からが適切」というのはありません。いつ始めても問題はないので、まずは軽い気持ちで始めてみましょう。
「0歳児には絵本の内容は理解できないのでは?」と疑問を持つ方もいるかもしれませんが、0歳児でも絵本の絵や色、形などを見て楽しむことができます。言葉の意味は分からなくても、絵本に出てくる音やリズムは五感を刺激し、豊かな感性を養っていきます。
また、絵本は子どもと大人のコミュニケーションや触れ合いの機会としても役に立ちます。
幼児教育としてだけでなくお互いの信頼関係、絆を深めるためにも、0歳や早期から絵本の読み聞かせを行うのがおすすめです。
絵本の読み聞かせをする効果
絵本の読み聞かせは、子どもの成長に大きく貢献すると言われています。具体的にどのような効果が期待できるか見ていきましょう。
読解力や言語能力を高められる
ひとりではまだ文字を読むことができない年齢でも、絵本の読み聞かせを通して絵を楽しみながら言葉に触れることができます。
日常生活ではなかなか耳にしない言葉も、絵本から習得していくことで次第に知っている言葉が増えていくでしょう。
また絵本により、読解力や言語能力が高まると、人の話を理解する「聞く力」がつくと同時に、自分の考えや気持ちを言葉にして「表現する力」を養うことができます。
豊かな感性を養える
読み聞かせを行うことで、言葉は分からなくても「心の脳」に直接働きかけることができます。
登場人物の気持ちを想像することで、うれしい、楽しい、こわい、かなしいなどの豊かな感性が育ち、 相手の気持ちを感じ、思いやりを持って人と接する心が養われます。
さらに想像力が豊かになることで視野も広がっていくため、何ごとも新しい視点で考える力を身につけられるでしょう。
集中力を高められる
子どもは集中できる時間が短く、すぐ別のものに興味が移ってしまいがちです。
しかし、絵本の物語が進んでいく中で「次はどんなことが起こるのかな?」自然と引き込まれていく経験を繰り返すことで、徐々に集中力が高まっていきます。
親子の関わりが増える
忙しい毎日の中で、わずかでも一緒に絵本を読むことを習慣にすると、子どもと向き合う大切な時間が得られます。
親に好きな絵本を読んでもらったり一緒に物語を楽しんだりする経験から、子どもは親からの愛情を感じ取り信頼関係も深まります。
読み聞かせにおすすめの絵本と選び方
絵本は、年齢や発達段階に合ったものを選んであげることが大切です。読み聞かせにおすすめの絵本と選び方を、年齢別に紹介します。
0〜1歳児の場合
0歳児は視力の発達段階であるため、まだぼんやりとしか見えていないこともあります。絵が大きく、色彩や形がはっきりとした絵本を選びましょう。
また「ワンワン」「モーモー」「ブーブー」「ワクワク」などの、リズム感があり擬音やオノマトペが多い絵本や、感触が異なる素材を指で触って楽しむ絵本、しかけの入った絵本もおすすめです。
オノマトペとは、自然界で発生する音や状態の変化などを模して表現する擬音語や擬声言語、擬態語などの総称です。
この時期には、見て、聞いて、触って楽しめる絵本を積極的に選ぶと、まだ言葉の理解が難しい赤ちゃんでも絵本を楽しむことができます。
じゃあじゃあびりびり
どんどこ ももんちゃん
2〜3歳児の場合
この時期の幼児は、言葉だけでなく体全体を通して絵本の世界と関わろうとします。
発声や視線、表情、姿勢、身振り、指差しなどのさまざまな表現方法を楽しむため、擬音やリズムを楽しめる絵本を積極的に取り入れていきましょう。
また、言葉の理解が進み、徐々にストーリ性のある絵本も楽しめるようになります。
おおきなかぶ ロシアの昔話
おじいさんが植えたかぶが、甘くて元気のよいとてつもなく大きなかぶになりました。おじいさんは、「うんとこしょどっこいしょ」とかけ声をかけてかぶを抜こうとしますが、かぶは抜けません。おじいさんはおばあさんを呼んできて一緒にかぶを抜こうとしますが、かぶは抜けません。おばあさんは孫を呼び、孫は犬を呼び、犬は猫を呼んできますが、それでもかぶは抜けません。とうとう猫はねずみを呼んできますが……。力強いロシアの昔話が絵本になりました。
まくらのせんにん そこのあなたの巻
驚きのしかけがあります。キャラクターが魅力的!読者参加型絵本。
ぞうさんに、きりんさん、うさぎさんに、たこさんと、次々と謎の穴にはまってゆく動物たち。「う~む。こうなったら、『そこのあなた』にたのむしかないな」と、自らも穴にはまった、まくらのせんにんさま。『そこのあなた』って、誰のこと?! そして、その先には、驚きのしかけが……!
人気絵本作家、かがくいひろしさんの遺作です。
4〜5歳児の場合
この時期の幼児は、想像力が豊かになり言葉のやりとりも上手になってくるため、理解して楽しめる絵本の幅も広がります。
ワクワク、ドキドキするような非日常の世界観や、ファンタジー要素のある絵本、冒険ものの絵本などを選ぶと、より想像力や創造力を育むことができるでしょう。
また5歳頃になると、数やひらがな、虫、花、自然、物の性質や地図など、ある特定の要素に興味を持つこともあるでしょう。
興味を持つと知識としてどんどん吸収できる時期でもあるため、子どもが選んだ好きなテーマに触れられる絵本を選ぶのもおすすめです。
ねえ、どれがいい?
「ねえ、どれがいい?」と問いかけながら、次々と繰り出される奇想天外な選択肢。
子どもたちは「どれもイヤ」と言いながら、大喜びであれやこれや悩みます。
30年近く愛され続けてきたベストセラー絵本の〈改訳新版〉。
絵本の読み聞かせをする際の注意点
 (1).jpeg)
絵本の読み聞かせにはさまざまな効果がありますが、より効果的に行うには以下の注意点も理解しておきましょう。
登場人物の過剰な演じ分けはしないようにする
大げさに声色や表情を変えたり、身振り手振りを変えたりすることで、子どもは絵本そのものではなく読み手に気を引き取られてしまうことがあります。
登場人物の特徴や違いを出したいからといって過剰な演じ分けはせず、声の大きさや高さなどでほんの少し変えるのみに留めておきましょう。
本の世界に没頭できるように、子ども自身の想像力を引き出してあげることが大切です。
絵本の絵がよく見えるようにする
絵本は、絵が見えるからこそ想像力が働くものです。読み聞かせの際は、子どもから絵がよく見えるような配置を意識しましょう。
絵本によっては、内容に合わせて絵本を揺らしたり降ったりする場面もありますが、集中力が欠けてしまうことがないように、必要以上に激しく動かすことは避けます。
絵本の絵を一緒に楽しみながら、読み聞かせを行うことが大切です。
ゆっくり・はっきりと読み聞かせをする
幼児期は、言葉や語彙力が育つ大切な時期です。リズミカルで美しい言葉の絵本を選ぶと同時に、ゆっくり・はっきりと読み聞かせを行うことも大切です。
無意識に早口にならないように注意し、心を込めて読んであげましょう。
絵本の読み聞かせをして子どもの成長発達を促そう
絵本の読み聞かせは、子どもの成長発達を促せるだけでなく、親子のコミュニケーションのきっかけにもなります。
読解力や言語能力、集中力、想像力のような学習の基礎となる能力、豊かな感性を養うほか、親子の信頼関係を深めるツールとしても役立つため、ぜひ積極的に取り組みましょう。
なお読み聞かせを行う際は、子どもが聞きやすい声や見やすい環境を心がけ、絵本の世界に没頭できるようにすることが大切です。
「いつから始めるべき」というものはないため、まずは気軽に始めてみましょう。

|
この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |




 絵本・本・よみきかせ
絵本・本・よみきかせ