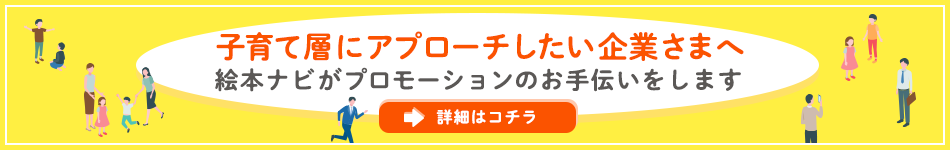子どもの一日は長い。
大人の一日は短い。
あの作業をして、この仕事をして。合間にお昼ご飯を食べて。気が付いたらもうこんな時間、家に帰らなきゃ。帰ったらあれしなきゃ、これしなきゃ。明日の支度もしなきゃ。そうこうしているうちに、あっという間に過ぎていく。
それでもたまに長い一日がある。嫌いな場所へいく、緊張する人と会う、初めての環境へ飛び込む。そういう日は汗をかきながら、やっとやっとで一日が終了するのです。
で、この長い一日が毎日ずっと続いているのが「子どもの一日」なのかな、と。
園や学校に行けば、ひっきりなしに事件が起きているし、何でもない日だって、新しいことだらけ。外に出れば初めてがたくさん。やることのない日の「ひまつぶし」だって、やることがありすぎる日の「うわのそら」だって、大人みたいにコントロールは出来ません。ご飯を食べるのだってひと仕事。朝、昼間、夕方。そして夜。それでやっと一日の終わりがやってきてお布団に入ります。
そんな子どもたちが、一日で一番楽しみにしている時間はなんだろう…。だから私は毎日ぎゅっと抱きしめます。例え5分だとしても、毎日じゃないとダメ。一週間まとめてなんて、ダメ。一日の終わりにぎゅっとするのです。今日も長い一日おつかれさまって。
子どもはどんな一日だって受けいれるし、その中でちゃんと楽しみを見つけていきます。その瞬間をとてもさりげなく、淡々と描いているのがこの絵本。
うみべのまちで
「ずっと暗い穴の中で働いてきたんだ、死んだら海の見える明るい場所に埋めてくれ」
海の見える町の、海の見える丘に、おじいちゃんのお墓がある。
おじいちゃんは、海の下を通るトンネルで、石炭を掘っていた。
今は、お父さんが同じように働いている。
そしていつか、ぼくもそこで働くんだ。
舞台のモデルは、1950年代のカナダのケープ・ブレトン島。
海辺に広がる炭鉱の町で、少年は暮らしています。
朝は友だちと遊び、昼には町へ買い物に出かけ、おじいちゃんのお墓参りをする。
そして夕方には、お父さんの帰りを待って、家族で夕飯を食べる。
この作品が描くのは、ただそれだけの、なにげない一日。
これは、コントラストの物語です。
お父さんが掘り進むトンネルの不気味なまでの不穏さと、地上で流れる日常の光景とのコントラスト。
一見不自由にも思える少年の未来と、しかしそのことに誇りを抱いているようにも感じる少年の言葉とのコントラスト。
炭鉱から漏れる炭で色のついたような黒々とした影と、日を受けてまばゆく光り輝く海とのコントラスト。
そのコントラストのなかで、ありふれた日常の愛おしさと、1950年という時代に若くして炭鉱で働き生きていくことの過酷さが、際立って読者の胸に迫ってきます。
淡々と、炭鉱と海と家族とに囲まれて過ごす、少年の一日を描いた絵本。
それなのに読後、胸に残るのは、まるでひとつの街とそこに暮らす人々の営みを記した壮大な一冊を読んだかのような感動です。
絵本でしか得られない、不思議な感動をぜひ、味わってみてください。
(堀井拓馬 小説家)
その生活が幸せかどうかを決めるのは難しい。でも、一日をかみしめながら過ごしているかどうか。意識するだけで全然違う毎日が訪れるのかもしれません。大人が子どもから学ぶことの一つです。
まだまだあります、「いちにち」の絵本
磯崎 園子(絵本ナビ編集長)

|
この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |




 絵本・本・よみきかせ
絵本・本・よみきかせ 








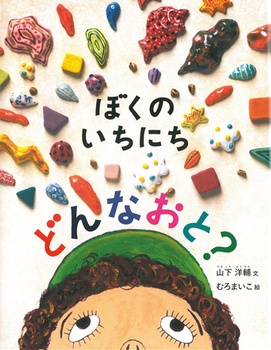








 ライフスタイル
ライフスタイル