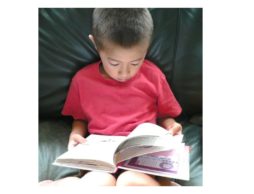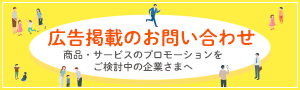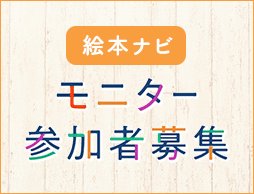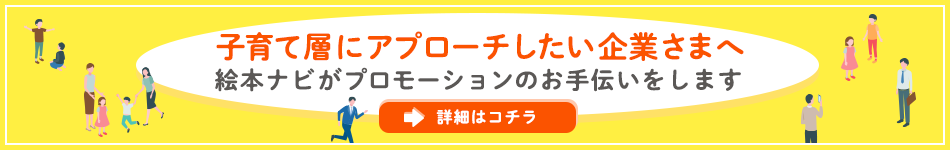子どもに贈るプレゼントの予算金額は?人気アイテムや注意点も紹介
 (1) (1) (1) (1).jpeg)
誕生日やクリスマスに子どもへ贈るプレゼントは、何を選べばよいか迷う方は少なくないでしょう。また、子どもに贈るプレゼントの一般的な金額、予算がどれくらいか気になる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、子どもに贈るプレゼントの予算金額を解説したうえで、プレゼントに人気のアイテムや注意点を紹介します。
子どもに贈るプレゼントの予算金額は?
子どもに贈るプレゼントについて、年齢別の金額相場は下記のとおりです。
| 乳児(0歳〜1歳) | 5,000円〜10,000円未満 |
|---|---|
| 幼児(2歳〜5歳) | 5,000円〜10,000円未満 |
| 小学生(6歳〜12歳) | 10,000円前後 |
| 中学生(13歳〜15歳) | 10,000円〜15,000円未満 |
| 高校生(16歳〜18歳) | 10,000円〜15,000円未満 |
プレゼントの金額は各家庭によって異なりますが、一般的に年齢が上がるにつれて、予算も少しずつ大きくなる傾向にあります。
しかし、プレゼントを選ぶ際、子どもの欲しいという気持ちを尊重する親が多いため、子どもが希望するアイテムによっては予算が大きく変わるでしょう。
子どもの誕生日やクリスマスのプレゼントに人気のアイテム
子どもに喜ばれるプレゼントを10選紹介します。プレゼント選びにお悩みの方はぜひ参考にしてください。
知育玩具
0歳から6歳ごろまでの子どもにプレゼントするなら、知育玩具が適しています。
知育とは、三育(知育・徳育・体育)のひとつであり、考える力や判断する力を伸ばすための教育です。子どもの将来の可能性を広げるためには、脳の発達が著しい幼少期に、年齢や成長に合った知育を行うことが大切です。
代表的な知育玩具には、積み木やパズル、ブロックなどがあります。また、知育につながる絵本もおすすめです。
マグネチック ポリドロン クリアタイプ スターターセット
ずけいであそぼ! カンタン! 自在! 教材クオリティ!
自由なアイデアをあそびながらカタチに!
正三角形・正方形・正五角形を、磁石でくっつけてあそぶ、図形学習教具に、半透明のクリアタイプが登場。
三角形をしきつめてみたり、正方形で立体をつくったり、
簡単、自在に楽しく遊べて、知らず知らずのうちに、思考力や図形センスが伸びる教具です。
知育の目的やいつから始めるべきか気になる方は下記の記事もご覧ください。
知育教育の目的や必要性は?おすすめの方法も解説します。
- 2023.08.10知育教育の目的や必要性は?おすすめの方法も解説

- 2023.07.07知育教育はいつから始める?効果や年齢別の内容も紹介

おもちゃ
おもちゃは子どもの年齢層にあったものを選びましょう。日本では、子ども用のおもちゃは、14歳以下の子どもが使う「玩具」と定義されており、安全面に配慮されたおもちゃにはST(Safety Toy)マークが表示されています。
おもちゃの種類は、ぬいぐるみ、ままごと用品、パズル、カードゲーム、ミニカー、三輪車などさまざまです。小さな子どもには、読み聞かせができる絵本もおすすめです。
リングカード・あいうえお
お豆のような曲線を描くやわらかなフォルム、鮮やかな色で描かれたシンプルで愛らしいイラスト、カラフルでポップなリング。
子どもたちが自分から「持ってみたい!」と思う楽しい仕上がりで多くの支持を集める戸田デザイン研究室のリングカードシリーズです。
「あいうえお」版は1歳くらいの小さな子どもたちも遊べるように、わかりやすく親しみのあることばを集めました。楽しみながらことばに触れていくことができます。好きなカードを数枚選んでリングでとめると持ち運びにも便利。出産のギフトにもぴったりです。
人形・ぬいぐるみ
人形やぬいぐるみは、生後間もない赤ちゃんや、本格的な「ごっこ遊び」が始まる3歳から4歳ごろの子どもにおすすめです。
小さな子どもに、人形やぬいぐるみを贈る際に気をつけたいのは「安全性」です。とくに、0歳から1歳ごろの赤ちゃんには、口に入らない大きさかどうか、怪我につながるような鋭利な部分はないかなどを確認しましょう。
絵本・知育本
絵本や知育本は、赤ちゃんから小学生の子どもにおすすめのプレゼントです。
成長のスピードによりますが、赤ちゃんは生後10ヵ月ごろから大人の声を聞きながら絵本を楽しむようになります。ゆっくりと読み聞かせをする時間は、親子にとって大切なコミュニケーションとなるでしょう。
また、知育絵本には音が出たり図形を動かしたりできるものがあり、子どもの思考力を伸ばすためにも役立ちます。
ぴたっとへんしんプレタングラム のりもの
三角や四角の5つのパーツで、車やヨットの形を作ろう!
タングラムとは、三角や四角のパーツで乗り物などの形をつくるシルエットパズルで、古くから知恵を伸ばす玩具として知られています。
子どもが遊び感覚ででき、考える力・集中力を伸ばすトレーニングになり、図形感覚を養います。
本シリーズは各巻ごとにパーツの形・数を変えたオリジナル版!
本に乗り物などの形の溝があり、そこにパーツをはめこんでいく仕組み。ついはめてみたくなるので、子どものやる気を引き出します。
5つのパーツで作れる形は無限大!
溝にはめ終わったら、自分でいろいろな形を作ってみましょう。
これはすいへいせん
谷川俊太郎×tupera tupera 初コラボ!
ことばが つながる たのしい “つみあげうた”えほん!
谷川俊太郎とtupera tuperaの初コラボレーション絵本。“これはすいへいせん”の一文から始まって、ページをめくるごとに、つぎの文がくっつき最後はとても長くなる、“つみあげうた”の言葉あそび絵本です。詩人の独特の語感とリズムにみちた言葉に、クラシックな世界観が新しいtupera tuperaの絵が応えます。ブックデザインは、新進気鋭のデザイナー岡田善敬。遊び心満載の装丁と造本にも注目です。
ゲーム
小学生から中学生までを対象とした国立教育政策研究所の「全国学力・学習状況調査」※によると、90%以上の小学生がゲームをしているという結果でした。小学生になると、誕生日などにゲームをリクエストされる場合もあるでしょう。
しかし、ゲームと聞くと、「成績が悪くなる」や「視力低下」などよくないイメージを持っている人もいるかもしれません。
ゲームを贈る際には、親子でゲームに関するルールを決めておくことが大切です。ゲームをする場所やタイミング、時間などをあらかじめ約束し、ゲームと上手に付き合っていきましょう。
さがしてみようみつけてみよう ゲーム・ブックno.1
しげみの中にかくれた動物たちを、ちょっとのぞいた耳やしっぽなどから、誰だかあてるゲームなど、楽しいアイデアいっぱいのゲーム絵本。
リュック・カバン・ポーチ
中学生・高校生になると、毎日の通学や塾通いに使うリュックやカバン、ポーチなどを贈ると喜ばれるでしょう。
勉強道具だけでなく部活動の道具など、多くの荷物を入れられるタイプが人気です。しかし、容量の大きさだけでなく、デザイン性や機能性も重視されます。
通学スタイルや本人の好みをリサーチし、気に入ってもらえるものを選びましょう。
アクセサリーやコスメ
女の子の場合、小学校低学年になるとアクセサリーやコスメに興味を持つようになります。
母親がメイクをしたり、アクセサリーでおしゃれを楽しんだりする姿をみて、真似をしたがる女の子は少なくありません。
最近では、多くのおもちゃメーカーから、キッズ用のコスメセットやアクセサリーが販売されています。ネックレスなどをハンドメイドするキットもあるため、作る段階から子どもと一緒に楽しめます。
洋服
洋服は、乳幼児から中高生まで、幅広い年齢層から喜ばれるプレゼントです。おしゃれに気をつかっている中高校生は特におすすめです。
しかし、洋服によっては、好みに合わなかったり、サイズが違うと着用できなかったりする場合があります。洋服を贈る際は、事前のリサーチをしっかり行うようにしましょう。
腕時計
小学1年生を迎える7歳以降の子どもには初めての腕時計を贈るのも良いでしょう。
小学校に通い始めると、時間を意識して行動する場面も増えてきます。小学校低学年から中学年の子どもに贈るプレゼントを考えている場合は、腕時計も候補のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
財布
小学生ごろになると子どもへお小遣いを渡し始める親も多いのではないでしょうか。
お金の管理能力を養うためには、子ども用の財布があるとよいでしょう。大切なお金を自分で管理する習慣がつき、お金への意識が変わるきっかけとなります。
近年ではキャッシュレス化が進み、子どもにとって「お金」の感覚が掴みにくくなっています。財布をプレゼントして家庭でのマネー教育を始めましょう。
子どもにプレゼントを贈るときの注意点
 (1).jpeg)
子どもへの贈り物を考えるとき、どのような点に気をつければよいか気になる方も多いでしょう。子どもにプレゼントを贈る際の3つの注意点を解説します。
プレゼントの金額や数が過剰にならないように注意する
子どもの年齢に見合わない高価なプレゼントを贈るのは避けましょう。
また、過剰な数のプレゼントを渡すのも、子どもにとってよいことではありません。高価な贈り物を数多くもらえることが、子どもにとって「当然」になってしまうためです。
子どもにお金の大切さを教えるうえでも、プレゼントの金額や数には気をつけましょう。
興味がないプレゼントを贈らないように注意する
プレゼントを選ぶ際、子どもが興味のあるものかどうかは重要なポイントです。
特に小さな子どもの場合、年齢に適していないおもちゃを贈っても、すぐに飽きてしまうかもしれません。また、誤飲などの事故を防ぐためにも、発達に見合ったプレゼントを選ぶことは大切です。
子どもに喜んでもらうには、事前のリサーチをしっかり行いましょう。
プレゼントの開封は子どもにさせてあげる
子どもにとってプレゼントの開封はワクワクした気持ちが最大限になる瞬間です。
子どもの年齢にもよりますが、ある程度物事の判断ができる年齢であれば、基本的にプレゼントはラッピングされたまま渡し、子ども自身で開封させてあげるようにしましょう。
プレゼントを開封するワクワク感を味わうことで、子どもにとって素敵な思い出として残るはずです。
子どもに贈るプレゼントは年齢に合わせた予算で考えよう
子どもに贈るプレゼントは、年齢に見合った金額のものを用意しましょう。子どもを喜ばせたい気持ちはもちろん大切ですが、プレゼントを通して、金銭感覚やものを大切にする習慣を身につけてほしいためです。
今回紹介したアイテムや注意点を参考に、子どもが喜べる素敵なプレゼントをぜひ選んでみてください。

|
この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |




 あかちゃん・こそだて
あかちゃん・こそだて 
 まなび
まなび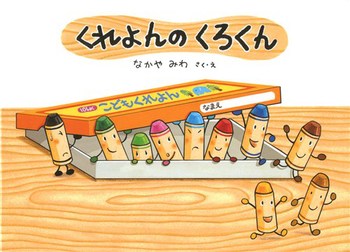




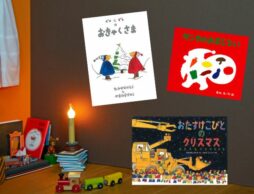



 絵本・本・よみきかせ
絵本・本・よみきかせ