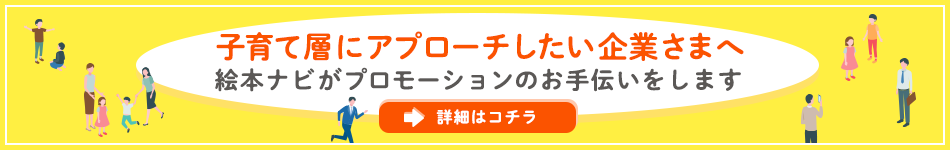生きるたくましさ、愉快さをあじわう物語。母と娘で語る、福音館文庫その3

福音館文庫、おすすめは? 母と小6娘でおしゃべりしました!
現実に疲れたら、遠いどこかの異国で違う自分になる空想をしてみませんか。たとえばナイル川のワニ、クロアチアの港街のみなしご……。「母と小6娘でおもしろかった本について語り合ってみました」連載企画、福音館文庫の第3弾は、たくましくしたたかに生きる様を痛快に描いた物語をご紹介します。傍から見たらちょっと残酷にみじめに思えたとしても、生き物は生きるためにあらゆることを試みます……。聖人君子じゃ生き抜けないから、この世界はおもしろいのかもしれません。小学校中・高学年以上、中高校生にも味わい深い本です。
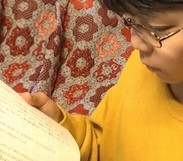
作家レオポルド・ショヴォーが、息子に語り聞かせた物語
10世紀もの年を経たワニは故郷を捨ててナイルを下り、海に出て12本足のタコと恋仲になるが…。苦いユーモアにみちた表題作ほか、「メンドリとアヒルの話」「おとなしいカメの話」など奇想あふれる全4篇を収録。
子どもを食べて太ったブナの大木と木こりが死闘を演じる表題作『子どもを食べる大きな木の話』をはじめ、誇り高いカタツムリの波乱にみちた生活を描く『大きなカタツムリの話』、ヘビが手足をなくしたてんまつを語る『ヘビの子の話』、字を読み書かきするほど天才的になった子グマの『小さなクマの話』など、とことん自在に物語の世界を広げる、レオポルド・ショヴォーが子どもたちに語ったお話5編。
母:『年をとったワニの話』と『子どもを食べる大きな木の話』は、小学3、4年生のときによく読んでなかった?
娘:そうそう。お父さんも昔読んだことがあって、好きだったんだって買ってきてくれたの。ショヴォー氏とルノーぼうやがおしゃべりする話で、その中に、さらに4つか5つ、おはなしが入っているんだよね。ショヴォーってこの本の作者なんでしょう。
母:レオポルド・ショヴォーは1870年生まれのフランス人で、お医者さんだったんだって。その息子のルノー君にむけて語ったお話に、自ら挿絵をつけた作品が、このシリーズ。1920年代から30年代にかけて発表された作品だから、最初にフランスで出版されたのはもう100年も前だねえ。
娘:『子どもを食べる大きな木の話』の表題作は、話も絵も印象的だった。ブナの大木の枝が子どもをひっつかんで、枝の間にぱくっと開いた口が子どもを飲み込むと、こぶみたいなものが、幹にそってぐりぐり下におりて消える場面とか。本当に食べられちゃった!という感じがした。切り倒された木のうろから、子どもがわーっと顔を出しているところも忘れられない。この白黒の絵、好きだよ。
母:消化されてこびとみたいに小さくなった子たちが、木の胃袋だった幹のうろからいっせいに顔を出す絵、いいよねえ。ペン画の繊細さと存在感、子どもたちを見下ろす木こりのおじさんの表情もいい!
あとお母さんは『年をとったワニの話』に出てくる「ノコギリザメとトンカチザメの話」と「メンドリとアヒルの話」がおもしろかったよ。
娘:あのふたつは私も好き。おもしろいよね。
母:でもさ……、ちょっとシュールっていうか、結構残酷だよね。ノコギリザメがクジラのあかちゃんをまっぷたつにして、お母さんクジラに追いかけられたり、トンカチザメが他の生き物を打ちころしたり……。メンドリがコウノトリにたのんで、自分のヒヨコたちに飛ぶ訓練をさせるのも「ヒヨコを飛ばせようとするなんて、無理でしょう!」と読みながら思っちゃったよ。
娘:うーん……そうかもしれないけど、意外と本当のことって言うか、事実に近いことが多いじゃない。親鳥が、ヒナに飛ぶ練習をさせるために巣から落とすっていう話を聞いたことあるよ。トンカチザメも、頭のかなづちみたいなところを、獲物を押さえつけるときに使うんじゃないの? 自然界ではふつうにあることがおはなしの中に混ざってて、残酷だとは思わなかったな。
母:なるほどー……。そんなふうに考えたことなかったな。だって『年をとったワニの話』の表題作の、ワニが恋仲になったタコの足を1本ずつ食べていく話だって、食べられながらタコが気づかないなんてありえないでしょう!? でも……ワニ(彼)には、タコ(彼女)のもも肉が、おいしそうで食べたくてたまらなくて、食べてみたらすごくいい味がして、ぜんぶ食べてしまって後悔の涙を流す……なんて、たしかに、ちょっとこわいくらいリアルだわ(笑)。
娘:ちょっとリアルなところと、変でおかしいところがいいんだよ(笑)。
母:そう言えば「ノコギリザメとトンカチザメの話」の中で、世界中の海や海峡の名前が出てきたの、わかった? ノコギリザメたちはお母さんクジラに追いかけられながら、紅海からスエズ運河、ジブラルタル海峡を通って太平洋へ逃げる。お母さんクジラは運河を通れなくてアフリカの喜望峰まわり。ノコギリザメたちは北極で涼んで、赤道まで逃げて、アマゾン川の河口で小休止とか……本当に世界の海を一周してて、ルートを想像しながら読むのもおもしろかったなあ。
娘:へえー、知らなかった! 世界地図を見ながら読んだらおもしろそうだね。
「ショヴォー氏とルノー君のお話集」シリーズ
みなしごたちが繰り広げる痛快な冒険物語
クロアチアの小さな港街を舞台に、みなしごたちが繰り広げる痛快な冒険物語。『長くつ下のピッピ』のモデルといわれ、ヨーロッパの子どもたちに愛されてきた不朽の名作。
ゾラと仲間たちは義賊ウスコックを名乗り、大人たちの裏をかき、盗みをし、したたかに生きていく。ところが、ある事件をきっかけに市長や警察から追われることになり……。
娘:『赤毛のゾラ』はとにかく本っ当に、おもしろかった! ゾラの仲間になってみたいと思ったよ。
母:ブランコ少年はお母さんが亡くなり、どこにいるのかわからないバイオリン弾きのお父さんも、冷たい祖母のカータばあさんも頼りにできない。お腹をすかせて落ちていた魚をひろったら、盗んだと言われ、警察に牢屋に入れられてしまう。牢屋から逃げ出す手助けをしたのが赤毛の女の子ゾラで、ブランコはゾラの仲間に入るのよね。
娘:もともとは金持ちカラマンがどろぼうだと言い立てただけで、街の人は、最初はブランコの敵じゃないよね。でもいざつかまると、昨日は一緒に遊んでたはずの仲良しの子も「どろぼう!」とはやしたてる……。
母:カラマンの顔色をうかがって、街の人がはっきりとは味方してくれないところ、人間社会のリアルだなあと思ったよ。でもブランコを助けたゾラと仲間のみなしごたちは、義賊風に「ウスコックの戦士」を名乗り、セニュの街を見下ろす古城をねぐらにして、自由に暮らすでしょう。警官に追いかけられてもへこたれず、仲間同士は義理堅く、正義感も強い。世間の目をかいくぐって子どもだけで暮らすのは楽しそうだよね。
娘:食べ物を盗むゾラたちを“街の敵”みたいに扱う人が増えていくけど、助けてくれる大人が何人かいるでしょ。たとえばパン屋のチュルチンは、一度どろぼうに入ったゾラの仲間のニコラをつかまえたとき、子どもだけで暮らしている事情を知って、毎朝古いパンをわけてくれるようになる。貧しい猟師のゴリアンじいさんは、盗んだにわとりを返しにきたブランコとゾラをつかまえて話を聞くと、漁を手伝わせてくれて、とった魚をちゃんと山分けしてくれる。
母:カフェや雑貨屋の主人、ホテルのドアマン、警官、林務官、農夫、市長の娘、金持ちたちの息子の中学生……。登場人物がたくさん出てくるけど、だれもが100%いい人でも、100%悪い人でもない。それぞれ会話に人間味があって、おもしろさがあるよね。好きだった場面はある?
娘:チュルチンのおかみさんの浮気騒動のところ(笑)。ゾラとブランコから、おかみさんが浮気してると聞いたチュルチンは、怒って相手を探し始める。実は、ブランコたちを追い回している警官のべゴヴィチが浮気相手で、パン屋の粉部屋で鉢合わせするんだよ。逃げ出そうとするベゴヴィチの情けない姿とか、ゾラとブランコが大人のベゴヴィチ相手に駆け引きする場面がおもしろかった!
母:お母さんはその前後の場面がドキドキしたなあ。いじわるな中学生に仕返しするため、ゾラたちが養魚池の水門をあけたことでコイとフナが大量に逃げて、大損害が出て、街中のうわさになっちゃう。「わー、それはまずいでしょう」とハラハラした。これまで味方してくれた大人も味方じゃなくなるんじゃないか、ゾラたちが完全に罪人扱いになるんじゃないかと。いよいよ頭にきた大人たちがゾラたちに懸賞金をかけて、さらにはゴリアンじいさんら地元猟師と水産会社の争いもあって、街中巻き込んだ大騒動に発展……。最後はどうなるんだっけ。
娘:最後には、子どもたちもそれぞれ居場所が決まるんだよ。街の人も、結局のところ、半分は子どもたちの味方だった。
なぜこんなにゾラの物語が好きだったのかなと考えてみると……、私は、子どもが、子どもだけでいいことも悪いこともたくさんして、それを公平に見てくれる大人がいるっていうのが好きなんだろうな。「いいなあ」と思う。正面から助けてくれるゴリアンじいさんみたいな人ももちろん好きだけど、横からちょっと助けてくれるチュルチンみたいな人や、口添えしてくれる司祭さんみたいな人がいるのがいいなと思う。
母:世の中にはイヤな大人もいるけど、子どもを対等な人間として見てくれる大人もいる。そういう人たちの中で生きていけるっていうのはすごくいいよね。ゾラたちの明るさや、知恵と誇りをもってしたたかに生きていこうとする姿が痛快!
海の情景も素敵だったなあ……。城から見下ろす海や、漁の夜明けの海、ゴリアンじいさんの家がある入り江……。イタリア側からじゃない、クロアチア側からのアドリア海をいつか見てみたい。ほら、アニメ『紅の豚』の舞台になっているアドリア海は、イタリア側から描かれているんだよ。
娘:え、そうだったの!? ゾラの海は『紅の豚』と一緒の海なのか。大好きなアニメ映画と本が同じ海を舞台にしているなんて。もう一回読みたくなっちゃった。
レオポルド・ショヴォ―は1870年生まれ。クルト・ヘルトは1897年生まれ。ともに19世紀生まれの作家で、2つの大戦を経験しています。
ショヴォーは第一次世界大戦に軍医として関わった期間中、長男と三男のルノー君(お話の聞き手である)を亡くし、戦後に怪物の塑像をつくったり、絵を描いたり、お話を書いたりしたそうです。フランスでは長いこと忘れられた存在だったようですが、近年は再び注目され、2020年の夏はパリのオルセー美術館で「Au pays des monstres(怪物の国で)」と題したレオポルド・ショヴォー作品展が行われています(2020年9月13日まで)。こちらの美術館のサイトでは、彼が描いた怪物たちが出てくる動画と、最後にはショヴォー氏の写真も見られますので、のぞいてみてください。(娘は「日本にも作品展が来たらいいのになあ」と言っています。親子でいつか見たい!)
ドイツ生まれの作家クルト・ヘルトは1933年にナチス政権の弾圧を逃れ、スイスへ移住。1941年に発表した『赤毛のゾラ』は『長くつ下のピッピ』のモデルになったとも言われ、ヨーロッパの少年少女に愛されてきたそう。作者がかつて滞在した港街セニュの情景を描いた、細部のリアルさが魅力的な一方で、「あとがき」によるとあえてリアルでない場面も入っているのだとか。たとえばゾラたちがおとずれた村の家畜市では、セルビア人、トルコ人、ユダヤ人、ダルマチア人など異なる民族の人が楽しそうに交流していますが、1940年代のクロアチアは人種差別政策が進み、当時のリアリティとはかけはなれた描写だったそうです。“ここに作者の伝えたかったことがある”と訳者の酒寄進一さんが書いています。大人も子どもも民族の違いも超え、人間を対等なもの同士として描こうとする作家だからこそ、『赤毛のゾラ』は今の私たちの心にも生き生きと届くのかもしれません。
子どもの目、大人の目。それぞれから見て味わう本の世界は、ひとりで読むよりずっとおもしろく、豊かに思えてくるから不思議です。『赤毛のゾラ』は80年、ショヴォーのお話集は100年という年月を生き残ってきた本。決して本ばかり読んでいるわけではなく、ゲームもマンガもアニメも好きな娘ですが、色眼鏡なしにおもしろいと思えば何でも手にとる姿に、たのもしさを感じます。子育て中に出会う本と言えば、絵本が定番ですが、実は高学年からのおしゃべりしながらの親子読書は、古今東西の物語に出会える、最高のチャンス! ぜひ、大人のみなさんも、いつもは手を出さない本にちょっと手を伸ばし、親子で同じ本を読む楽しみを味わってみてくださいね。
文・構成:大和田佳世(絵本ナビライター)
編集:掛川晶子(絵本ナビ編集部)

|
この記事が気に入ったらいいね!しよう ※最近の情報をお届けします |




 絵本・本・よみきかせ
絵本・本・よみきかせ 



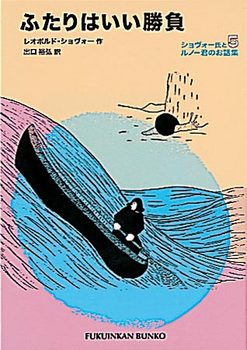









 グッズ・ギフト
グッズ・ギフト 

 あそび
あそび